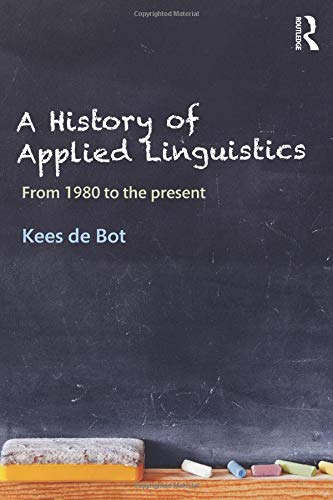今書いている予稿集原稿の草稿をアップします。
--------
今後の言語政策研究に必要な論点:英語教育政策研究を事例に
-
はじめに
英語教育界では「21世紀はグローバル化の時代であるから云々」という未来予測めいた言説が蔓延しているが、過去15年の状況(グローバル経済危機、保護貿易主義の台頭、そして、世界的パンデミック)を見れば、それがいかに大胆すぎるかは自明だろう。本発表では未来予測はあえて放棄して、言語政策のメタ的な次元である研究インフラについて論じる。 すなわち、社会の予測不可能な変化にも柔軟に対応できるような研究インフラとして今から構築しておくべきものは何か論じたい。
なお、本発表では、筆者の専門分野である英語教育政策研究(事例・理論・方法論)を前提に、言語(教育)政策研究のあり方について論じる。 もっとも、以下の内容は、他の言語や非教育領域の言語政策にも大いにあてはまるとは思うが、何らかのズレも認められるだろう。そうした論点についても積極的に意見交換したい。
とくに本稿では、重要なテーマとして次の3点を指摘したい。それは、(1) 狭義の言語教育政策に関するメカニズムの研究、(2) 基礎資料としての統計調査の必要性、そして、(3) 「エビデンスに基づく政策決定」論への対処である。以下、順番に説明する。
-
狭義の政策の記述的研究
英語教育政策の研究で、今後、とくに必要である(しかし、蓄積は遅れている)と思われるのが、狭義の政策――つまり、中央政府・地方政府が権力を(民主的に/しばしば非民主的に)用いて、共同体のメンバーに特定の行為(この場合は英語教育関連の行為)を強いること――のメカニズムに関する研究である。
言語政策研究は、公共政策研究と比して、「政策」を緩やかに定義する傾向があり(Hult & Johnson, 2015, Spolsky, 2009)、英語教育政策研究についても、広義の政策――とりわけ、英語や英語教育をめぐるイデオロギーの分析、英語教育現場の政策受容、学習者や教員のアイデンティティ、保護者の英語教育戦略など――については研究が進んでいる。 しかしながら、日本の教育政策をとりまく政治状況を考えると、狭義の政策に対する研究蓄積はかなり心許ない。 というのも、2010年代以降、政策過程は官邸主導の名のもとに集権化がすすみ、ともすると非民主的に政策が決まるリスクを抱え込みつつあるからである(河合, 2019)(英語教育政策に関しては、寺沢 2020, 江利川 2018)。 したがって、恣意的な政策決定への対抗戦略として、狭義の政策に対する研究が不可欠である。以下、「政策」はすべて狭義の政策の意味で用いる。
適切な政策批判のためには、政策メカニズムの理解が不可欠であり、政策内容の単なる記述や、分析に基づかない批判研究(印象批評的な批判)では不十分である。 具体的には、政策決定プロセスの研究(いわゆる政策過程論の射程)、実施プロセスの研究(政策実施論、そして、財政や法律・条例などに注目した行政学的分析)、政策効果検証(教育社会学・教育経済学)がとくに重要と考えられる。
-
基礎統計としての調査
政策決定あるいは政策批判の基礎資料となるべき統計(社会言語学的統計)の整備も遅れている。 たとえば、英語使用ニーズに関する質の高い統計は教育課程を構想するうえで最も重要な情報の一つだが、英語教育(政策)研究者は自前の調査を組織してきておらず、社会科学者グループが行ってきた社会調査を二次利用せざるを得ない状況が続いている(寺沢, 2015)。
なお、調査の質を高める要因は多数あるが、とりわけ次の2点は重要であり、そしてこれまでの研究ではあまり考慮されてこなかった。 第1が、代表性である。調査データから妥当な推論をするためには、調査回答者ができる限り母集団の縮図に近いことが望ましい(吉村, 2017)。なお、代表性は、社会調査分野では最重要視される論点であるが、言語政策・応用言語学では比較的軽視されているように思われるため、この点の啓蒙も必要である。 第2が、設問の明晰さである。 設問の測定対象は明確であるべきであり、曖昧さは極力低減する必要がある。 測定の透明性が高いほど、その後に他の研究者に再利用されやすくなるため、転用可能性が高まり、研究コミュニティ全体に利益をもたらす。
近年、日本内外でエビデンスに基づく政策決定(EBPM)に関する議論が盛んである。 日本でも、行政の一部で、この考え方を積極的に取り入れようとする動きが見られる(大橋, 2020)。
問題は、EBPMは、言語政策分野にとって、追い風にもなればトロイの木馬にもなり得る点である。 追い風とは、EBPMには、政治家の思いつきに代表される恣意的な政策決定を民主的に軌道修正できる力が(すくなくとも理屈上は)あることである。 一方、トロイの木馬とは、「この施策にはエビデンスがない。ならば、廃止すべきだ」というように、コストカットの根拠として悪用されかねない点である。 実際、言語(教育)政策の多くはその意義が見かけ上は分かりづらいものが多い。 ここには、(a) エビデンスの偽陰性の問題 ――つまり、本当は効果がある(たとえば長期的あるいはマクロ的に)にもかかわらず、短期的・ミクロ的な効果に注視した実証研究では効果が見いだせないという問題、 および、(b) そもそも効果の観点から合意形成が困難な価値(権利や美学的価値)が教育分野には多数含まれるという問題がある。
筆者は、前者、つまり、追い風の観点から、これまでの小学校英語の政策決定のあり方を批判したが(Terasawa, 2019)、後者の観点も同様に重要であるだろう。 いずれにせよ、今後、エビデンス/EBPMは行政的キャッチフレーズとして、大きな影響力を及ぼす可能性があるため、言語政策学界も、対抗言論を丁寧に用意しておく必要がある――たとえば、「数字で教育は語れない」などというナイーブな認識論ではあまりに脆弱であり、EBPMの認識論的立場を正確に理解したうえで、批判を展開すべきである(Bridges, Smeyers, & Smith, 2009; 杉田・熊井, 2019)。
参考文献
- 江利川春雄. (2018). 『日本の外国語教育政策史』ひつじ書房.
- 大橋弘. (2020). 『EBPMの経済学:エビデンスを重視した政策立案』東京大学出版会.
- 河合晃一. (2019). 「文部科学省と官邸権力」青木栄一編『文部科学省の解剖』(pp. 97–134). 東信堂.
- 杉田浩崇・熊井将太. (2019).『「エビデンスに基づく教育」の閾を探る:教育学における規範と事実をめぐって』春風社.
- 寺沢拓敬. (2015). 『「日本人と英語」の社会学:なぜ英語教育論は誤解だらけなのか』研究社.
- 寺沢拓敬. (2020). 『小学校英語のジレンマ』岩波書店.
- 吉村治正 (2017). 『社会調査における非標本誤差』東信堂.
- Bridges, D., Smeyers, P., & Smith, R. (2009). Evidence-based education policy: What evidence? What basis? Whose Policy? Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Hult, F. M., & Johnson, D. C. (2015). Research methods in language policy and planning : a practical guide. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
- Spolsky, B. (2009). Language management. Cambridge University Press.
- Terasawa, T. (2019). Evidence-based language policy: theoretical and methodological examination based on existing studies. Current Issues in Language Planning, 20(3), 245–265.